今出回っているハニトラ政治家報道について、中国政府や中国報道官が公式に「日本の政治家を公表する」と発言した事実は、現時点では確認できません。
この手の話、SNSではかなり強い言葉で流れてきますよね。
「中国報道官が脅した」
「名簿を公開すると宣告した」
そう聞くと、正直ちょっとゾワッとします。
私自身も最初にX(旧Twitter)で画像を見たときは、「え、マジ?」と思いました。
こんなのに釣られていたら情報工作され放題だぞ…。
— 保守系まとめサイト『正義の見方』 (@honmo_takeshi) November 22, 2025
【デマ注意】限界系界隈、中国報道官が「ハニトラにかかった政治家、コメンテーターを公表する」と発言したかのような捏造画像を大拡散し大盛り上がり…フィフィ、倉田真由美氏、北村晴男氏も引用 https://t.co/EKpM5cOYyS pic.twitter.com/cl7YKf5ee6
ただ、落ち着いて一次情報を当たってみると、空気がガラッと変わります。
中国外務省の公式発表が掲載される中国外交部公式サイト や定例記者会見の全文が載る 中国外交部報道官談話、さらにそれを引用する 共同通信・時事通信・NHK などの主要メディアを確認しても、「日本の政治家をハニトラで公表する」といった発言は見当たりません。
一方で、
zakzak や coki.jp、Yahoo!リアルタイム検索 などが扱っているのは、「そうした画像や動画が拡散している」という現象の報道です。
どの記事も、よく読むと「真偽不明」「フェイクの可能性」「火元は確認できていない」
という表現にとどまっています。
ここが大事なポイントです。
公式に確認された発言と、SNS上で広がっている噂は、同じニュース枠に見えても中身はまったく別物。
それなのに、
「中国報道官」という肩書きが付いた瞬間、
一気に本当っぽく見えてしまう。
人って、立場のある名前や、もっともらしい画像に本当に弱いんですよね。
だからこの記事では、
「怪しい」「怪しくない」を感情で決めません。
まずは
✔ 公式に確認できる情報は何か
✔ まだ噂の段階の話はどこか
この線をはっきり引くところから始めます。
怖い話題ほど、一歩引いて事実と噂を分けて見る。
それだけで、見え方はかなり変わります。
現時点で「公式に確認できる事実」と「噂」は分けて見るべき
今回SNSで広がったのは、主に3種類の素材です。
1つ目は、
中国の報道官の名前や肩書きを記した静止画像。
背景に国旗や会見風のデザインが使われ、日本語で
「ハニトラに関わった政治家を公表する」
といった強い文言が添えられていました。

2つ目は、
その画像を元にした短い動画。
テロップ付きで読み上げる形式になっており、数十秒ほどで内容が分かる作りです。
井川意高氏が語る中国のハニトラ #政治 #shorts #ショート
3つ目が、
それらを引用したSNS投稿やまとめ記事。
X(旧Twitter)では、画像付き投稿が短時間で拡散され、Yahoo!リアルタイム検索でも関連ワードが急上昇しました。
スパイ防止法
— 今日からシュウジ (@grate_dragon) July 24, 2025
なぜか反対する政治家が多いんですよね。
ハニトラや利害関係で操られてるなら、もはや希望の気配が見えません!
報道の自由です
「プライバシー」どころの話ではありません。
誰かにハメられた
と言われる
中川昭一 酩酊会見の様に、言動が怪しい政治家居るけど違法薬物使ってない? pic.twitter.com/XUGRcBBNYL
これらに共通しているのは、
✔ 発言日時が書かれていない
✔ 会見名・資料番号がない
✔ 中国外交部公式サイトへのリンクがない
という点です。
一方、zakzak や coki.jp、japanlooks.jp などのメディアは、
「中国政府が発言した」とは書かず、「そのような画像や動画が拡散している」事実のみを報じています。
つまり、今回広がった情報の正体は、公式発表そのものではなく、SNS上で流通した画像・動画。
まずはここを押さえておくと、話が整理しやすくなります。
公式情報で検証:本当に中国報道官の発言は存在するのか
中国報道官の発言かどうかは、調べる場所が決まっています。
そして、そこを見れば「ある・ない」はかなりはっきりします。
まず確認すべき一つ目は、
中国外交部(外務省)の公式サイトです。
ここには、報道官による定例記者会見の全文が、ほぼ毎回テキストで掲載されます。
日時・会見名・発言者名が明記されていて、あとから編集された形跡も残りません。
次に見るのが、
共同通信・時事通信・NHKといった通信社・公共放送。
中国報道官の発言で日本に影響が出る内容なら、このあたりがほぼ確実に拾います。
特に共同通信は、中国外交部会見を定点で追っているため、発言があれば数時間以内に記事化されることが多いです。

ここまで見て、
・公式サイトに記録がない
・通信社の記事も出ていない
この2点がそろった場合、
その時点で「公式発言として確認できない」と判断して問題ありません。
よくある誤解が、
「動画があるから本当」
「画像がリアルだから公式」
という考え方。
でも実際は、公式発言ほど
文書・記録・引用元がきっちり残るものです。
もう一つの判断材料が、
メディアの書き方。
新聞社や通信社が「中国報道官は〇〇と述べた」と断定しているか、
それとも
「SNS上でそのような画像が拡散している」と距離を取っているか。
ここは文章を一行読めば分かります。
もし公式発表が見当たらない場合は、
「今は確認できる情報がない段階」
それ以上でも以下でもありません。
黒でも白でもなく、グレーのまま保留が正解です。
怖いのは、公式情報が出ていないうちに「言ったらしい」「やるはずだ」と話を進めてしまうこと。
事実確認は、早さよりも場所が大事なんです。
ここまで押さえておけば、次に似た話題が出てきても、慌てずに自分でチェックできます。
報道・メディアの扱い方を比較:断定しているのはどこか
今回のハニトラ政治家報道を「断定」している主要メディアは、ほぼありません。
温度差があるだけで、立場はかなりはっきり分かれています。
まず、新聞社や通信社。
朝日新聞、読売新聞、毎日新聞、共同通信、時事通信。
このあたりは一貫して慎重です。
もし中国報道官が日本の政治家について具体的に言及していれば、
「〇日、北京で行われた定例会見で〜と述べた」
という形で、発言日時・会見名・肩書き込みで報じます。
でも今回は、それがない。
次に NHK。
ここも同じで、公式発言が確認できない話題については、基本的に「政府がこう発表した」とは書きません。
仮に触れるとしても
「SNSでこうした情報が拡散している」
という現象の紹介にとどまります。
一方で、空気が変わるのが
ネットニュースやタブロイド寄りの媒体です。
zakzak、SmartFLASH、一部のまとめ系サイトなどは、「拡散」「波紋」「騒然」といった言葉を使い、話題性を前に出します。
ただし、よく読むとここでも「真偽不明」「フェイクの可能性」という逃げ道はきちんと残している。
この違い、かなり大事です。
断定しているように見えて、実は断定していない書き方なんですよね。
さらに個人ブログやSNSになると、「これは確定」「裏で決まっている」と一気にトーンが強くなる。
でもそこには、
一次情報や公式資料へのリンクがないことがほとんどです。
つまり、今回の報道を並べて見ると、
● 新聞・通信社:事実確認が取れないものは踏み込まない
● 公共放送:公式発表ベース以外は距離を取る
● ネット・タブロイド系:話題性は出すが断定は避ける
● SNS・個人発信:言い切りが増える
この構図がはっきり見えてきます。
もし本当に重大な公式発言があったなら、新聞と通信社が一斉に横並びで報じます。
それが起きていない時点で、少なくとも「事実として確定した話ではない」と判断していい。
ニュースを見るときは、
内容だけでなく
「どのメディアが、どんな温度で書いているか」。
ここを見るクセがつくと、
噂に振り回されにくくなります。
読者向けチェック項目:噂を信じる前に確認する5ポイント
噂に振り回されない一番の近道は、この5つを順番に確認することです。
難しいことはありません。慣れると1分もかかりません。
① 出どころはどこか(最初に出したのは誰?)
まず見るのはここ。
朝日新聞・読売新聞・毎日新聞、共同通信、時事通信、NHK。
このあたりが一切触れていない話は、かなり慎重に扱った方がいい。
逆に言うと、重要な公式発言なら、最低でもどこか1社は拾います。
② 日付とタイミングは明記されているか
「いつの話か分からない情報」は要注意です。
公式発言なら、
✔ 日付
✔ 会見名
✔ 発言の場
が必ずセットで出てきます。
それがない画像や動画は、今の話に見せかけただけの可能性が高い。
③ 発言者の肩書きは具体的か
「中国報道官」「関係者」「政府筋」
この書き方だけで終わっていたら、一度ブレーキ。
公式なら
「中国外交部 報道官 ○○氏」
のように、名前と立場がはっきり書かれます。
デリピックス 冷凍弁当 ミシュランシェフ監督 定番人気6種×2(12食セット)野菜がとれるおかず 惣菜 宅配 レンジで5分
④ 一次ソースにたどり着けるか
元ネタへのリンクや引用はありますか?
中国外交部公式サイト、会見全文、通信社の記事など、元を確認できない情報は、基本噂止まりです。
「動画がある=一次情報」ではありません。
⑤ 言い切り表現が多すぎないか
「確定」「暴露」「ついに公表」「間違いない」こうした強い言葉が連発されている場合、
内容より感情を動かす目的の可能性が高い。
実際、zakzak や coki.jp でさえ、こういう話題では「真偽不明」「可能性」という表現を使っています。
この5つをチェックして、どれか一つでも引っかかったら、即シェアしない。
「保留」にして正解です。
噂は早く信じた人が勝ちじゃありません。
最後まで冷静だった人が、だいたい正解を引きます。
怖いのは噂そのものより、確認せず拡散すること
結論をもう一度はっきり言います。
今回のハニトラ政治家報道で一番怖いのは、噂があることではなく、確認されていない情報が「事実っぽく」広がってしまうことです。
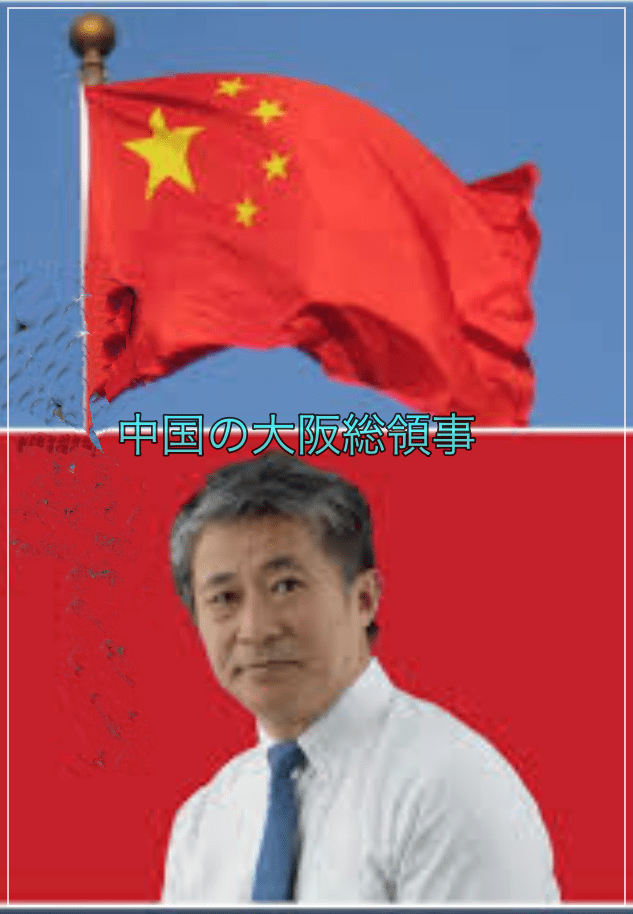
中国報道官の発言とされる話も、中国外交部の公式サイトや、NHK・共同通信・時事通信といった主要メディアを確認する限り、現時点で公式に裏付けられた情報は見当たりませんでした。
それでも、SNSでは画像や動画が先に走り、Yahoo!リアルタイム検索では関連ワードが短時間で上位に並ぶ。
このスピード感が、判断を一段と難しくしています。
でも、ここまで読んできた人なら、もう分かるはずです。
大事なのは「信じる・信じない」を急ぐことじゃない。
一度立ち止まって、確認する場所を思い出すこと。
・公式発表はどこに出るのか
・主要メディアはどう書いているか
・言い切りではなく、慎重な表現になっていないか
これを一つずつ見るだけで、不安はかなり整理できます。
噂は、放っておいても勝手に生まれます。
でも、拡散しなければ大きくはならない。
だからこそ、
「今は保留でいい」
そう判断できる人が、一番冷静です。
次に似た話題を見かけたときは、この記事のチェックポイントを思い出してください。
噂を追いかける側ではなく、噂を整理できる側に回る。
それが、この手のニュースと付き合ういちばん賢い距離感です。
-150x150.jpeg)
こちらも人気です!
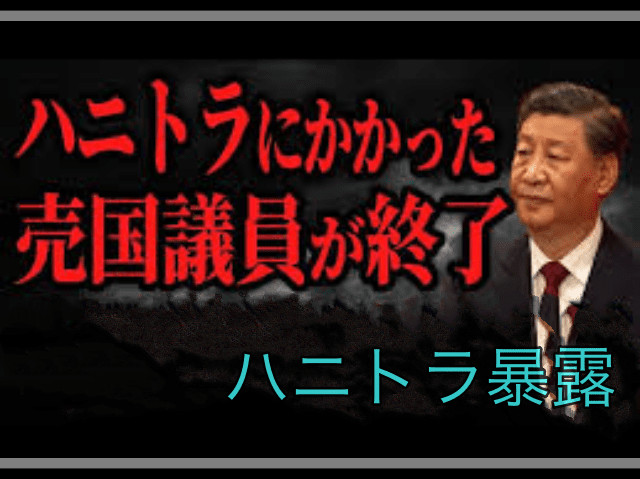
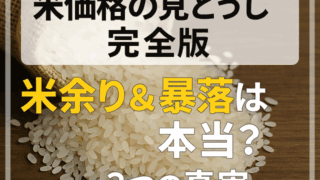
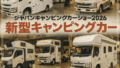
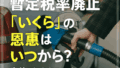
コメント