ガソリンの値段が上がったり下がったりして、ついニュースを見てしまうことはありませんか。
とくに
「暫定税率が廃止されたら、いくら下がるのか」
「いつから変わるのか」
という部分は、生活にすぐ直結するので気になるところだと思います。
わたし自身も、給油のたびに価格の差を見ては、少しでも負担が軽くならないかなと考えてしまいます。
そんな中で、ガソリンの話ばかりが広がる反面、灯油の税金がどうなっているのかは、
意外と知られていないままになりがちです。
とくに冬場は、灯油の使用量が増えるので、価格の変動が家計にダイレクトに響きます。
それなのに
「そもそも灯油にはどんな税金が含まれているのか」
「ガソリン税の暫定税率が動いたとき、灯油の値段も変わるのか」
といった疑問は、調べようとしても説明がバラバラで分かりにくいものが多いです。
知らないまま支払いを続けるより、仕組みを知っておいた方が、
ニュースの意味がつかみやすくなりますし、値動きにも冷静に向き合えるようになります。
家計の負担が少しでも軽くなるヒントを見つけやすくなるので、ぜひ参考にしてみてくださいね。
暫定税率の基本!廃止で何が変わる?

長年ガソリン価格に上乗せされてきた「暫定税率」が廃止されることで、
私たちの暮らしはどのように変わるのでしょうか?
まずは、ガソリン税の仕組みと、今回の廃止の意味について、分かりやすくご説明いたします。
🔳 ガソリン税の「本則」と「暫定」の違い
ガソリンの価格には、様々な税金が複雑に含まれています。
その中心にあるのが「ガソリン税」で、これは揮発油税と地方揮発油税という二つの税金から成り立っています。
このガソリン税には、
「本則税率(ほんそくぜいりつ)」と
「暫定税率(ざんていぜいりつ)」
という二つの異なる税率が設定されていますよ。
本則税率(基本の税率)
法律で定められたガソリンにかかる本来の税率のことです。現在、ガソリン1リットルあたり約28.7円がこれにあたります。
暫定税率(上乗せ分)
これは、道路整備などの財源を確保するために、一時的な措置として本則税率に上乗せされてきた部分です。現在は1リットルあたり約25.1円が上乗せされています。
つまり、私たちが今ガソリンスタンドで払っているガソリン税(消費税を除く)は、
この本則28.7円と暫定25.1円を合わせた約53.8円となっているのです。
今回の「暫定税率廃止」とは、この上乗せ分の25.1円がなくなることを意味します。
-150x150.jpeg)
2025年11月現在、ついに暫定税率の廃止法案が参議院本会議で可決・成立しました。これにより、ガソリンの暫定税率(25.1円/L)は2025年12月31日をもって正式に廃止されることが決定しています。
🔳 廃止が議論される理由とメリット
なぜ、これほど長く続いた暫定税率が今、廃止されることになったのでしょうか?
最大の要因は、近年の物価高騰と家計負担の軽減です。
なぜ、これほど長く続いた暫定税率が今、廃止されることになったのでしょうか?
最大の要因は、近年の物価高騰と家計負担の軽減です。
- 家計の負担軽減: 暫定税率が廃止されれば、ガソリンの店頭価格が恒久的に引き下がります。これにより、自家用車を利用する世帯では、平均で年間約12,000円もの負担軽減が見込まれており、大きなメリットになりますよ。
- 物価の安定化: 物流や運送業界の燃料コストが削減されることで、最終的にスーパーやコンビニで販売される商品の価格にも良い影響を与え、物価上昇を抑制する効果が期待されています。
- 税制の公平性: 暫定税率は道路財源から一般財源へと使途が変わった歴史があり、その課税根拠に対して「二重課税ではないか」という疑問の声も長らくありました。廃止は、そうした税制の公平性を求める声に応えるものでもあります。
このように、暫定税率の廃止は、単にガソリン代が安くなるだけでなく、
日本経済全体のコスト削減や家計のゆとりを生み出す、大きな転換点となりそうですね。
【最重要】廃止は「いつから」適用される?

ガソリン価格が下がるのはいつからなのか、最も気になる部分ですよね。
最新の情報では、暫定税率の廃止日は確定しましたが、
その効果はすでに補助金の拡充という形で現れ始めています。
価格の変動スケジュールを詳しく見ていきましょう。
🔳 ガソリン税廃止の最新決定スケジュール
長年の議論を経て、ガソリン税の暫定税率(特例税率)は、ついに廃止が決定しました。
最終決定日
2025年11月28日に、廃止を定めた関連法が参議院本会議で可決・成立しました。
ガソリン暫定税率廃止日:減税額
2025年12月31日をもって正式に廃止されます。
1リットルあたり25.1円の税負担がなくなります
※ざっくり整理すると、ガソリンまわりの大きな日付はこの3つです。
2025年11月13日〜:補助金 15円/L に拡充
2025年12月11日〜:補助金 25.1円/L(暫定税率と同額)
2025年12月31日:暫定税率廃止・補助金も終了
この決定により、2026年1月1日からは、ガソリンにかかる税金は本来の本則税率のみに戻る仕組みです。
約半世紀続いた制度に区切りがつけられたことは、私たちの家計にとって大きなニュースといえるでしょう。
🔳 適用開始日と補助金との複雑な関係
「12月31日に廃止なら、年明けから急に25.1円安くなるの?」と思われるかもしれませんが、
実は価格への反映はすでに始まっています。
これは、「燃料油価格定額引き下げ措置」(通称:補助金)が段階的に引き上げられているためです。
この補助金は、ガソリン価格が高騰した際に、
小売価格を抑制するために石油元売りに支給されていたものですよね。
政府は、暫定税率が廃止されるまでの期間、この補助金を徐々に増額し、
実質的な価格引き下げ効果を先行して実現させるという方針をとっています。
| 実施日 | 補助金(1Lあたり) | 実質的な減税効果 |
|---|---|---|
| 〜2025年11月12日 | 10円 | 10円 |
| 2025年11月13日〜 | 15円 | 5円増額 |
| 2025年11月27日〜 | 20円 | 5円増額 |
| 2025年12月11日〜 | 25.1円 | 5.1円増額(暫定税率相当額に到達) |
| 2025年12月31日 | 補助金終了 | 暫定税率(25.1円)が正式に廃止 |
このように、補助金は12月11日には暫定税率の25.1円と同額にまで引き上げられ、
実質的な負担軽減は年内に完了するスケジュールです。
そして、12月31日に補助金が終了するのと同時に暫定税率が廃止されるため、
「補助金終了による値上がり」と
「税率廃止による値下がり」が相殺され、
年明けに急激な価格変動が起きることを防ぐ仕組みとなっています。
クリスマス お肉料理のオードブル 2025 銀座ポルトファーロ プレミアム「珠玉」 2-3人前 全21品【12/22(月)お届け】※12/20,21着も対応可
🔳 軽油の暫定税率廃止は「いつから」か?
ガソリンの暫定税率が注目されがちですが、
ディーゼル車に使われる軽油にかかる税金(軽油引取税)にも暫定税率が上乗せされています。
この上乗せ分は1リットルあたり17.1円です。
軽油引取税の暫定税率についても、廃止の時期が決定しています。
軽油暫定税率廃止日
2026年4月1日をもって正式に廃止されます。
減税額
1リットルあたり17.1円の税負担がなくなります。
軽油の場合もガソリンと同様に、廃止までの間は補助金が段階的に拡充され、
2025年11月27日には、すでに暫定税率相当額の17.1円に補助金が到達しています。
軽油は主に物流や運送業界で利用されるため、
このコスト削減は全国的な物価安定効果に直結することが期待されています。
スケジュール感は次の通りです。
● 2025年11月27日:軽油の補助金が 17.1円/L に到達(暫定税率分と同額)
● 2025年11月27日以降:実質的には暫定税率分を補助で相殺した状態
● 2026年4月1日:暫定税率を正式に廃止、同時に補助金も終了
※ 結論・・・・・・・・・・・
- ガソリンの「いつから?」は 2025年11月〜12月にかけて実質値下げ → 12月31日に暫定税率が法的に終了
- 軽油の「いつから?」は 2025年11月末から補助で実質相殺 → 2026年4月1日に正式廃止
という二段構えになっている、というイメージを持っておくと分かりやすいと思います。
「いくら」安くなる?家計の負担軽減を計算

ガソリン価格の変動は日々の暮らしに直結するため、具体的にどれだけの節約効果が期待できるかを知りたいですよね。
暫定税率が廃止されることで、
ガソリン価格から1リットルあたり約25.1円の税金がなくなるだけでなく、
消費税の軽減分も加わり、さらなる家計の負担軽減につながります。
🔳 ガソリン1Lあたり期待できる減税額
ガソリンにかかっている税金は、「揮発油税」と「地方揮発油税」の合計で構成されています。
このうち、暫定税率として上乗せされていたのは、1リットルあたり25.1円です。
この暫定税率が2025年12月31日に正式に廃止されると、価格から単純に25.1円が引かれることになります。
この25.1円の減税は、価格が高騰した際の一時的な措置ではなく、恒久的な税負担の軽減
となるのが大きなポイントです。
しかし、注意したいのは、価格の店頭への反映にはタイムラグがあることです。
廃止前の補助金拡充策によって、すでにこの25.1円分の軽減は実質的に適用されているため、
年明けに価格が急激に下がるというよりは、恒久的な値下げ水準に移行すると考えるのが適切でしょう。
🔳 消費税込みで「いくら」安くなるのか
ガソリン価格には、税金(本則税率+暫定税率)に対してさらに消費税が課されています。
これは、しばしば「二重課税」として議論される点です。
暫定税率25.1円が廃止されると、
その25.1円に対しても課税されていた消費税(税率10%)も当然かからなくなります。
- 暫定税率の減税額:25.1円
- 消費税の軽減額:25.1円 × 10% = 約2.51円
つまり、1リットルあたり約27.6円(25.1円 + 2.51円)の負担軽減効果が期待できる計算となります。
例えば、現在のレギュラーガソリンの全国平均価格が170円だと仮定した場合、
暫定税率廃止後の価格水準は、原油価格や為替の変動がないとすれば、
約142円から143円程度になる見込みです。
この減税効果は、家計に直接的なメリットをもたらします。
マッスルデリ【MAINTAIN】 たんぱく質 35g以上 冷凍弁当 (管理栄養士監修/男性向け) 栄養食 弁当 5食セット
🔳 年間走行距離から節約額をシミュレーション
では、この約27.6円/Lの減税効果が、あなたの家計にどのくらいの節約をもたらすか試算してみましょう。
仮に、燃費を1リットルあたり10kmとして計算した場合の年間節約額の目安は以下のとおりです。
| 年間走行距離 | 年間ガソリン消費量 (L) | 年間節約額の目安 (約27.6円/Lで計算) |
|---|---|---|
| 5,000 km (週末ドライバー) | 500 L | 約13,800円 |
| 8,000 km (平均的な通勤・通学) | 800 L | 約22,080円 |
| 15,000 km (長距離通勤・営業利用) | 1,500 L | 約41,400円 |
政府の試算でも、1世帯あたりの平均負担軽減効果は年間約12,000円とされていますので、
日頃から車を多く利用される方や、地方にお住まいで車が必須な世帯にとって、
この税率廃止は非常に大きな恩恵となることが分かります。
この節約分を他の生活費に充てたり、貯蓄に回したりといった柔軟な選択肢が生まれることにつながるでしょう。
意外と知らない「灯油」の税金知識5選

冬場の暖房に欠かせない灯油も石油製品ですが、ガソリンや軽油とは税制上の扱いが大きく異なっています。
ガソリン税の暫定税率廃止のニュースを聞いて「灯油も安くなるのでは?」
と思われた方も多いかもしれませんが、灯油の価格構造は、
実は非常にシンプルな税金で成り立っているのです。
🔳 灯油には「暫定税率」が適用されない理由
結論から申し上げますと、灯油にはガソリンに課せられていた「暫定税率」(当分の間税率)は、
そもそも一切適用されていません。
ですから、仮にガソリンの暫定税率が正式に廃止されても、灯油の価格が税制面で下がることはないのです。
なぜ灯油は対象外なのでしょうか?
それは、日本の税制が灯油を、特に寒冷地における
「生活必需品」や
「命を守るための燃料」
として位置づけてきた歴史的経緯があるためです。
移動手段としての側面が強いガソリンとは異なり、
暖房用の灯油に対しては、高額な税金を課すことが人々の生活に大きな支障をきたすと考えられてきました。
このため、ガソリンが税金を含めると複雑な二重課税構造になっているのに対し、
灯油は非常にシンプルな税制が維持されているわけです。
今回話題になっている「暫定税率(当分の間税率)」の対象となる燃料は、主にガソリンと軽油。
灯油には、この暫定税率は課されていません。
この背景には、
「揮発油税」
「地方揮発油税」
「軽油引取税」
といったガソリン・軽油専用の税制度の構造があるためです。
これらの税は、車両用の移動燃料にあてられるもので、
灯油のような暖房用燃料はもともと別扱いのため、暫定税率の対象外となっています。
そのため、たとえガソリンや軽油の暫定税率がゼロになっても、
灯油の税金構造そのものは変わらない というのが重要なポイントです。
灯油を使う家庭では、「今回の廃止=灯油安くなる」という期待は、基本的に誤解にあたります。
🔳 灯油にかかっている税金(石油石炭税など)
では、灯油にはどんな税金がかかっているのか。
主に以下のような構成になっています。
● 石油石炭税(石油製品全般にかかる国税)
● 地球温暖化対策税(環境対策のための追加税)
● そしてそれらに対する 消費税
この組み合わせにより、灯油1リットルあたりの税負担はごくわずか。
一般的には 約2.8円/L とされています。
たとえば、ガソリンでは税金分だけで1リットルあたり50円以上になるケースもあり、
灯油の税金がいかに軽いかが比較で浮き彫りになります。
つまり、灯油価格の大半は
「原油コスト」
「精製コスト」
「流通コスト」
「需要と供給のバランス」
で決まっていて、税金の占める割合はとても小さいのです。
「灯油が高い=税金が高い」という風潮は、実際の税負担を考えると誤解であることがわかります。
🔳 灯油価格の今後の見通しと変動要素
灯油の価格は、ガソリンの減税議論とは無関係に、国際的な要因によって大きく変動します。
今後の価格を予測する上で特に重要な変動要素は以下の3点です。
1, 原油価格:当然ながら、灯油の原料である原油の国際価格(WTIやドバイ原油など)が最も大きな影響を与えます。OPECプラスの協調減産や地政学的リスク(中東情勢など)の高まりは、原油価格を高止まりさせる要因となります。
2, 為替相場(円安):原油はドル建てで取引されます。そのため、歴史的な円安傾向が長期化している現状では、原油の輸入コストが跳ね上がり、灯油価格も高水準で推移する可能性が高いです。
3, 冬の気温と補助金の動向:国内の暖房需要がピークを迎える真冬の気温も価格に影響します。また、政府は現在も灯油を含む燃料油に対して**激変緩和対策としての補助金(定額5円/L)**を実施していますが、この補助率の今後の調整や終了の時期も、末端価格を左右する重要な要素となります。
2025年冬の時点では、円安と原油高の影響を受け、
灯油価格は引き続き高値圏で推移することが専門家によって予測されています。
| 年間変動要因 | 影響 |
|---|---|
| 原油高・円安 | 輸入コスト増により価格高止まり |
| 政府補助金(5円/L) | 急激な値上がりを抑制する効果 |
| 冬場の気温 | 寒ければ需要が増え、価格上昇の可能性 |
この情報を踏まえ、灯油をご利用のご家庭では、
高値圏での推移を前提とした賢い購入タイミングや
暖房効率を上げる節約術がより重要になってまいります。
まとめてみると、灯油は“税金”じゃなく“コスト”で動く燃料
● 灯油にはガソリン・軽油のような「暫定税率」は適用されていない。
● 税金は石油石炭税+環境税+消費税あわせてごくわずか(約2.8円/L)。
● 価格の決まり手は原油価格、精製コスト、流通経費、需要と供給など“実コスト”。
● したがって、今回の暫定税率廃止は灯油の値段には直接の影響なし。
廃止の裏側:財源問題と今後のガソリン価格

ガソリン税の暫定税率がなくなると、家計は助かりますが、
当然その裏では
「失われるお金」と
「どこから埋めるか」
という話が動いています。
🔳 減税によって失われる「いくら」の財源
まず押さえたいのが、国全体としてどれくらいの税収が消えるのか という点です。
試算では、ガソリン税の暫定税率をやめると 年間で約1兆円、
軽油引取税の暫定分も含めると 合計で約1.5兆円 の税収減になると見込まれています。
このお金は、もともと
● 道路や橋、トンネルなどインフラ整備
● 公共交通の維持や補助
● 一般会計に回して財政赤字を抑える役割
といったところに使われてきました。
そのため、暫定税率を完全にゼロにすると、
「道路の修繕が遅れるのでは?」
「地方のバス路線が維持できなくなるのでは?」
といった不安も同時に出てきます。
では、この 1.5兆円規模 の穴をどう埋めるのか。
与野党の議論では、
● 大企業向けの租税特別措置(研究開発減税など)の見直し
● 高所得者や金融所得への課税強化
といった案が候補に挙がっています。
つまり、「ガソリンで取るのをやめて、株など“もうけ”側に少し重くのせる」という方向性が検討されているわけです。
🔳 廃止後のガソリン価格の予期せぬ変動要素
「25.1円の暫定税率が消えるなら、単純に25.1円安くなるよね?」と考えたくなりますが、
現実はもう少し複雑です。
資源エネルギー庁のQ&Aでもはっきり書かれていますが、
暫定税率が消える当日に、価格がそのまま25.1円ストンと下がるわけではありません。
理由は、政府がすでにガソリン価格に 定額補助金 を入れていて、
それを段階的に増やしたり止めたりしながら、価格のショックをやわらげているからです。
さらに、ガソリン価格には次のような要素も強く効きます。
● 原油価格の変動(中東情勢や世界的な需要で上下)
● 為替レート(円安になると輸入原油が高くなる)
● 競合スタンドとの価格競争(地域差が出やすい)
● 在庫の仕入れタイミング(安いときに仕入れたか、高いときに仕入れたか)
このため、税金の部分だけを切り取って見ても、
実際の店頭価格は「下がる力」と「上がる力」が混ざった結果 として動きます。
シミュレーションでは、暫定税率25.1円分にかかっていた消費税約2.5円も含めて、
理論上は1リットルあたり約27.6円の負担軽減 になるとされていますが、
これもあくまで「他の条件が変わらなければ」という前提つきです。
つまりユーザー目線では、
「確かに前よりは安くなったけど、ニュースで聞いた数字ほどではない」
「原油高が重なって、思ったほど下がらない時期もある」
というケースも普通にありえる、というイメージでいたほうが現実的です。
ガソリン暫定税率廃止法が成立しました!
— 足立康史 国民民主党 参議院議員 (@adachiyasushi) November 28, 2025
昨年10月に続き、本年7月にも明確な「民意」を示してくださった党員・支持者の皆さま、そして広く国民の皆さまに、改めて深く感謝を申し上げます。… https://t.co/mlJIKkmBoA pic.twitter.com/VLD3gdKIPY
🔳 暫定税率廃止に関するよくあるQ&A
最後に、よく聞かれそうな疑問をまとめておきます。
Q1. この減税は“ずっと”続くの?
→ 暫定税率を廃止する法律自体は恒久的なものとして決まりますが、別の名目の税や環境負担金が将来新設されないとは言い切れません。
財源不足が長引けば、他の形での増税や負担増の議論が出る可能性は常にあります。
Q2. 軽油や灯油、高速料金も同じように安くなる?
→ 軽油にはガソリンと同じように暫定税率があり、こちらも別スケジュールで廃止が決まっていますが、灯油にはそもそも暫定税率がかかっていません。
高速料金はガソリン税とは別の仕組みなので、今回の減税だけで直接安くなる話ではありません。
Q3. 減税で物価はどのくらい落ち着くの?
→ マクロの試算では、暫定税率廃止による減税規模は 1.0〜1.5兆円 程度と見込まれ、物流コストの低下を通じて物価の押し下げ効果が期待されています。
ただし、同時に「炭素価格(実質的な環境税)が弱くなる」という指摘もあり、脱炭素の流れとのバランス が今後の大きなテーマになりそうです。
家計負担を減らすための給油タイミング

● 補助金が段階的に上がるうちに給油を
今回、ガソリンの暫定税率廃止に向け、政府は11月13日から補助金を順次拡大してきている。レギュラーガソリンだと、まず15円、次に20円、
最終的に暫定税率相当の25.1円に引き上げる予定。
この期間は「店頭価格が理論上かなり安くなるタイミング」。
給油の予定があるなら、この波に乗るのが吉。
特に郊外や車通勤の多い人ほどメリットが大きいはずだよ。
● 年末までの“駆け込み給油”には注意を
ただし、補助金→廃止後の税制変更完了までは駆け込みで価格が上がったり、
スタンドによっては在庫状況で割高になる可能性もある。
だから「補助金で安いから満タンに!」と無計画に入れると、あとで「あれ?」となるかも。
🔳 暫定税率廃止後の灯油の価格動向
● 灯油はそもそも暫定税率の対象外
これまで説明してきたように、灯油にはガソリンのような暫定税率はかかっていない。
だから、今回の廃止で「灯油が安くなる」という直接の恩恵は基本的にない。
● 灯油価格は“世界の原油相場”や“需要と供給”に左右されやすい
灯油の価格を決めるのは、税金ではなく主に
原油価格、精製コスト、流通・配送コスト、季節による需要の変動。
たとえガソリンが安くなっても、灯油は別の要因で上下するのが常。
● 灯油を使うなら“購入タイミング”と“保存・節約術”で賢く対応
冬前など価格が上がりやすいタイミングを避けたり、
ストーブの使い方を工夫して燃費をあげたり。
灯油は“使い方”がそのままコストに響く燃料だから、節約の余地は大きいよ。
🔳 今後の税制改正の動きに注目!
● 財源の穴埋め策は今後の大きな争点
今回のガソリン・軽油の暫定税率廃止で、国と地方あわせて
年間約1.5兆円もの税収減 が見込まれている。
この穴をどう補うか――法人税の見直し、金融所得課税の強化、脱炭素の観点からの環境税導入など、案は様々。
どれが選ばれるかで、将来の燃料コストや物価全体にも影響が出る可能性がある。
● 燃料価格は「税金+国際原油+為替+物流コスト」で決まる複合要素
税制だけに注目しても不十分。
世界情勢や為替、輸送コスト変動の影響で、ガソリン/灯油ともに「値下げ後に再上昇」というパターンもあり得る。
だから、「安くなった=安心」ではなく、常に幅を見た予算設計が大事。
● エコや脱炭素の流れも視野に:クルマ・暖房の使い方を再考するチャンス
燃料コストが変わる時期は、同時に「車に乗る頻度」「暖房の使い方」「省エネ設備」
などライフスタイル全体を見直すいいタイミング。
今後は税制だけでなく、環境政策や消費行動の見直しも合わせて考えると、
より賢く、持続可能な暮らしにつながると思う。
-150x150.jpeg)
こちらもどうぞ!
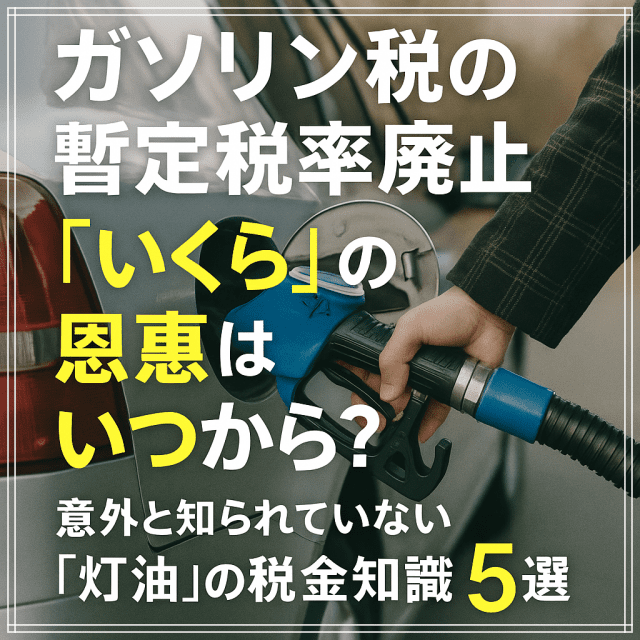





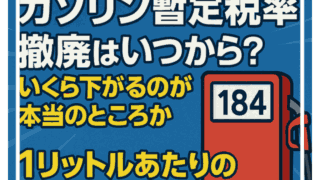
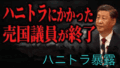
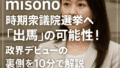
コメント